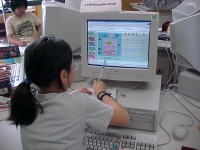「OKNetからインターネットへ」
(学校インターネット事業修了報告 2004/3 より)
1.研究のねらい (1)総合的な学習の時間での、学び方の指導とあわせた児童の情報活用能力の育成 |
(1)ネットワークメディアの中心としての「OKNet (Oyama Kodomo Network)」校内LANを活用して、児童がすべての学習や活動の中で情報活用能力を伸ばす基礎的な活用を図っている。OKNetは、その中に設置しているHPである。学年のページ、学習リンク集、検索のページ、子ども掲示板等を設置して、コンピュータ・ネットワークを活用した学習の出発点として児童の利用を進めている。 |
|